


 。
。 (永ザマ)
(永ザマ)  (ツギザマ)
(ツギザマ)  (美ザマ)
(美ザマ)

 。
。漢字の我が國に傳來したのを、日本書紀には應神天皇の十六年の事として有る(紀元九百四十五年)が其は表向きのことで、實際は其の以前から已に傳はつて居たらうと言はれる。この時、漢字の起つた支那から直に傳へられたので無くして、我が國と言語の系統を同じうする百濟人から傳はつたから其の讀方や發音に於て國語に取り入れられ易いことになつて居たらうとも考へられるが、百濟にての漢字學習の歴史が十分に傳はらぬので之を確言しかねる。
これまで口から耳へ傳へるまでで、之を書き留める方法を有たなかつた我等の祖先は、喜びと驚きとで漢字を受入れようとしたが、我が國とは言語の系統を異にする他國に發生した文字で有つた爲にいはゆる圓い孔に四角な栓をするやうな風でシツクリとゆかなかつた。だから喜びは消し飛んで驚きだけ殘つた形で、直に我等の祖先の用には立たなかつた。
佛教が傳來(欽明天皇の十三年、紀元千二百十二年)した事も漢字に親しむ氣運を高めたので有らうが、聖徳太子(―紀元千二百八十一年)の頃になつて、始めて漢字を吾が物にした事實が明かに存在して居るのは、傳來以來三百四十年間の我等の祖先の撓みなき努力が其の效を奏したものと敬服すべきで有る。
受入れられなかつた物が今や受入れられたので有る。絶縁状態で有つた兩者の間に電氣が交流し出したのだから、漢字の日本化は此に其の第一歩を蹈み出した。
漢字は支那人が其の言葉を寫す爲に造り且つ用ひて來た文字で有り、漢文は此の漢字を其の言語に存する語法及び文法によつて綴り成して、思想や感情を陳べる文章で有る。だから其の漢字や漢文の讀方は支那人のを標準として之に從ふべきは論を竢たない所で有る。漢字漢文がいかに古くから我が國に傳來して居るとは云へ、我が國で之を外國語もしくは他國の文章として取扱つたものなら、漢字の讀方も漢文の讀方も支那の其を標準とすべきことは猶獨逸人や英人が今日漢字漢文を學ぶがごとくで有るべきだ。
然るに支那語として學習した人人を除いた大多數の我が國民の漢字漢文の讀方は全く支那人の其とは別途のものとなつて居る。故に漢文を作るに長じて筆を執れば萬言立ちどころに成る人でも支那人と會話するを得ぬが普通となつて居る。
といふ文章は全部漢字より成立ちて、之を讀むにも全部音讀するのだから、漢文かと云へば、支那人には理會し得ぬ文章で有るのは、支那人の語法文法によりて綴つて居らぬ爲で有る。此く大膽に國語の語法を以て漢文を扱つたらしきは已に聖徳太子の頃の文獻に存する。
漢文の形をなして居り乍ら、眞の漢文では無いものの存するのは、漢文を國語の語法によりて讀み換へた結果で有る。漢文を國語の法則によつて讀むには、其の主語・述語・客語の順なるものを主語・客語・述語の順に改めねばならぬ等々の事が起る。この讀み換へる事は何時頃から起つたか、之を詳にしがたいが、聖徳太子の頃には文章の末の部分に國語の風に讀んだ痕迹をのこして居る。
讀み換へるにしても、一度は原文のままに讀みて折返し國語で其の意を陳べるといふ方法も有る。多分此ういふ方法が長く用ひられたらうが、後には國語で其の意を陳べるものだけとなつたのが、今の漢文訓讀法だ。古の文章語と口語との別れなかつた時代には、訓讀即ち其の意を述べるものだつたらうが、今日は訓讀の外に又「講義」が必用となつて居る。其はとにかく他國の言語文章を全く自國の語法文法によりて讀みこなし(消化)て居るとは世界廣しとも恐らく類例の無い事だらう。此の場合の漢字漢文こそ日本化を通り越して日本的の物だ。即ち漢字漢文を他國の文字文章と看做さずして、我が國に於ける第二の文字・文章と親しみ拔いた結果で有る。
漢文を讀み
之をやつてのけた我々の祖先だもの、漢文を讀み解いた外に個々の漢字についても大膽極まる取扱をした。即ち漢字は其の性質として、文字の構成の内に其の意義を藏して居るのに、其の性質にはお構ひなく單に我々の發音を表すのみの物に轉向させてしまつた。之には無論支那にて佛經を譯する時梵語を寫すに漢字を單に表音文字に用ひたのが其の參考となつたらう。此くて表れたものはいはゆる
漢字を日本的ならしめたこととして、私は此の二つが最も重なるもの、之よりして其の形にも音にも義にも種々の日本化が起つたと考へる。私は毎に「漢字は東洋のエスペラント」だと信じて居る。隨て今日も其の發生した支那以外にも、又今日は已に滅亡した國(西夏、契丹)にも使用せられたが、此く日本的にしたのに比すべきものは少ない。この事は我が國民の文化的一大業績として高く評價せらるべきでは無からうか。
漢字漢文を日本化した一方には、我々の思想法も漢文化した。前の文章も國語なら
といふべきを、あの短さで意が通ずるのは、漢文モドキの
此く漢字を單に發音を表はすものに流用し、又漢文を我が語法のままに讀み解いた此の二線に沿ひて派生した多くの事項を以下形、音、義、熟語等の四方面に分けて述べる。但し他國語を取人れる際に避けがたい事(例へば支那の南方系の音らしい呉音、唐代の首都たりし長安系の音を傳へたる漢音、又宋以後のを移した唐音がそれ〳〵原のまゝでは有り得なかつた類)や、受入れて後に起つた變化(萬葉假名の成立時代にはア行のエとヤ行のエとに、平安朝の中頃までは撥ねる音のンとム其の別が有つたに、逞に其が混ぜられた類)は之を避けて、日本化せしむる意志の加はつた事項に止める。
漢字が文字としていかなる風に日本化したらうか。之には五つの場合が考へられる。
漢字に似せて造られたもので、閊や峠は字の組立に意義を求められるが、多くは其の成立を解しかねる。
天武天皇十年(紀元千三百四十二年)に新字一部四十四卷を造らしめたと日本書紀に見えるので、(近來は此の種の文字が段々支那の字書にも載せられて居る)此等の和字が其の新字かとも考へられるが、一部四十四卷といふ大量には上るまじきこと、其の當時の文献に遺つて居る和字が少ないことよりして直に然りと定めかねる。
我が國にて作れる文字にして、同じき形が支那の字書にも存することあり、此の時其の意義の相異なるは論を竢たず。
支那の字書にては下段にて釋せる如き意義だが、吾が國の用法は之と異なる。寄り加はりて話の相手などする人。花の形の牙齒に似たるより艸冠に
我が國の事情によつて漢字の構成の一部を變へたるもの有り
古文矛字と有り。その金扁を木にかへる。
石杠と有るは往來に關係ある字だから彳の扁、今は其を木にて遣るとて木扁に變へた。謂 ㆓之 徛 ㆒
二字を合せて一字とするもの。秦時代の鐘銘に小子(小子)亖方(四方)など有れば、支那に起つた事だが、後世には用ひられない。然るに吾が國にては長く用ひられて、二字合せられたとは普通に知らぬ者も多い。
と有りて女官の名だつた采女を我が國のウネメ(宮中の下級の女官)の名稱に用ひ、且之を合せて 婇 と書く。置 ㆓美人、宮人、采女 三等 ㆒
「又田 陳也、樹 ㆑穀 曰 ㆑田 」
「と有りて、田と地との解の近きを見ると、我が國にて田と云へば水田とするとは異なるらしい。水田ならぬ耕地にはヤキハタとて春先に其處の草などを燒いて地を肥やす方法が有りて之を火田とも云つたが、後には水田ならぬを火田と稱することゝなりて火田はおのづからハタケを表はすことゝなつた。白樂天の詩に地 萬物所㆓陳列 ㆒也」
と有る。其處は乾燥して土色白いから白田とも後漢書に出て居る。この白田、火田を合せた字を我が國ではハタケ。人 納 ㆓火田 租 ㆒
漢字の艸體に於て



 。
。 (永ザマ)
(永ザマ)  (ツギザマ)
(ツギザマ)  (美ザマ)
(美ザマ)

 。
。と書き分けて尊卑を別ち、書翰にて
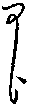 (可被下候)
(可被下候) 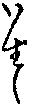 (御座候)
(御座候)  (參らせ候)
(參らせ候)と略するの類も、漢土の人の夢想せぬ所だ。彼の平假名もこゝに入れても可い。
漢字の音は其の漢字の有する意義を表はす支那の言葉で有る。他國の發音を受入れる時に純然と原のものの如くには受入れかねて、若干の變化が起ることは已むを得ぬ。漢字が我が國に傳はつた時も亦同樣で、我が國に存在しない音に對しては便宜な方法が用ひられた是が漢字の音に於ける日本化で有る。其の主なるものは
當時我が國に存せざりし音の處置に二種あり。
ng の音が無かつた爲に、之をウで表はした。東 tong をトウ、洋 yang をヤウの類。但し之には此の場合のウが今日のウと同じき音だつたか否やの疑が有る。後に相サウを
當時我が國の發音に無かつたのは其に近いものに移して表はした。
支那には七音三十六字母と云つて、字音の初頭には三十六の種類有りとせられる。然るに我が國では、之を
の十四種に發音するのみだから、頗る粗な道理で有る。
又四聲の別は漢字の呼法に於て重要な事だが、其の平、上、去の三聲は之を移すを得なかつた。支那では、東董凍、支紙寘、眞軫震は平、上、去聲に呼び分けたが、我が國にては倶にトウ、シ、シンと寫すのみだつた。
かと思ふと又恐ろしく精微なのが有る。石塚龍麿の研究によると
| え | き | 清 | け | 清 | こ | 清 | そ | と | 清 | ぬ | ひ | 清 | へ | 清 | み | め | よ | ろ |
| 濁 | 濁 | 濁 | 濁 | 濁 |
の十三音(古事記にはこの他「ち」 「も」の二も)は二種に分れて、例へば「よ」では
などの語の間には越ゆべからざる別が立つて居る。龍麿は此の前者を用、後者を余で代表せしめて居るが、韻鏡でいふと此の用余の二字は倶に喉音清濁行即ち喩母に屬するから、音韻の上より何とも別が立つまい。なほ此の用余は代表字だから各〻の語を寫すに用ひられた文字は用には欲庸容、余には與豫譽預などが有る。
我が國では子音で畢る發音が無かつた爲に、適宜母韻を添へた音に變つた。
| 福フK | 沒ボT | 法ハP |
| 徳トK | 突トT | 答タP |
| 覺カK | 骨コT | 急キP |
| 速ソK | 出シユT | 集シP |
| 郁イK | 聿イT | 揖イP |
の K T P をク、ツ、フとせる類。
カ、ス、トなどを
などが有る。此等は普通ジヤ、シウ、ジヨ、リヤウ、リウと讀むのだから、直音に變へて用ひて居る。
字音は其音尾(韻)によつて三内に分れる、喉内 ng 、舌内 n 、脣内 m が其れ。此の ng に母韻を添へて我が國にてガ(相模)ギゴ(愛宕)グ(香)とも用ひたは已に觸れたが、地名郡名の記載法としてはまだ〳〵自由に用ひて居る。
| 舌内 n | ||||
|---|---|---|---|---|
| 脣内 m | ||||
| 印 |
惠 |
|||
又 K T P の音尾をクツワの外に曲げたる
| 安 |
佐 |
( |
||
| ( |
||||
| ( |
字音がウで終るもの、又 ng を原音とせぬ一類の音尾をワ行に曲げたる
字音には開合の別が有り。合音とはワ行又は其の拗音で寫すことになつて居る
| 開 | 安アン | 加カ | 看カン | 渇カツ |
|---|---|---|---|---|
| 合 | 椀ワン | 果クワ | 觀クワン | 括クワツ |
大言海の凡例十八に
烏 永 詠 榮 垣 等は姑く舊慣の假名遣によりて「え、えい、えん」とせり
と云つた所の烏等は合音で有る。所が兄、狂も亦合音なれば、之をケイ、キヤウ(開音の假名)と呼ぶ前にはクヱイ、クヰヤウ(合音の假名)と呼んだもので、ケ、キは其のクヱ、クヰの約まつたのだと説明するを要するので有る。隨て歴史的字音假名遣といふも此の約まつた後の記録と云はねばならぬ。開合は字音では重要な者だから、之を遵守せぬは甚しき日本化で有る。
この他
漢土にて全く同音なる文字を、我が國にては別々に取扱ふのが有るのも、其の何れか一方が日本化した道理となる。
| 王眷切 | 胡男切 | 是執切 | 直六切 | ||||
| 莫厚切 | 即略切 | 召舒切 | 徒含切 | ||||
又一句一章の中に並び存するを區別する爲に
又同類に並び存するを混雜せしめぬ爲に
國語に存する音便法を字音の上にまで推し及ぼしたものも有る。
又
外國語を學習する時に自國語に譯して其の理會を助けるは自然の事で有る。但し其の譯は理會を助ける方便に過ぎざるべく、主體が其の外國語の讀方たるべきは論を竢たぬ。然るに我が國では漢字本來の讀方には觸れないで、いはゆる譯即ち訓のみで理會してしまふのだから、この訓も即ち漢字を日本化して居ると見て可いのだが、今は字引で普通に國訓といふものに止めて置かう。其は支那の字引には載せざる意義を我が國にて認めて居るもので有る。
「凡そ自ら稱するに、士の大夫に於ける(大夫に臣事する士)は外私と曰ふ」と有るは自稱だ、其も私のみを用ふるので無い。
「相呼びて誘ふなり」と有るが本義で、註文の義はなし。
「水を以てと有るもので、寂寞の義なし。沃 ぐなり」
支那の字引に見ゆる訓義だが、今は我が國にてのみ用ひるもの
支那の字書には同字異體とせるものを、我が國にて別途の用法とするもの
我々の名即ち
信の字の
良の字の
も右の如くに説明すれば其の本づく所を得られるが、果して之が當つて居るや否や。
支那には二字若くはそれ以上の熟語が多い。我が國でも其等を取入れたは勿論、且盛に之を作つて居る。支那では戰爭の理想的に正しいのは義戰だが、之に滿足せずして聖戰、理想と信念とを搗き合せて理念、完成と遂行とで完遂、妥協と終結とで妥結など、毎日の樣に新語が登場するが、中には半こなれで喉に引かかりさうなも有るは苦苦しい。
先づ國語が本になりて成立つた熟語を其の日本化したものとして擧げよう。
國語を寫すにいかめしき漢字をあてゝ熟語の觀をなすもの
龜生毛、兎生角の字を用ふ。
漢語を國語に讀み解いて
などともした。和歌には漢語のまゝでは讀み入れられぬから起つた事で、明治の初にも蒸汽船を「むせいきの船」と詠んだ歌人も有るさうな。定めし力をも入れずして
之を逆に往つて國語に漢字を充てゝ、其の漢字によつて國語の義を解いたも有る。
鍛冶之音誤倭名類聚抄の序文の一句、鍛冶をかぢ(鍛治)と音するは誤りとの意。蓋し「かぢ」は渉 ㆓鍛治 ㆒
も「源君謂㆘誤㆓㆐讀鍛冶㆒爲㆗鍛治字音㆖者非㆑是」と云つた。
昔兄弟左右の大臣在りけるを、相人見て立樣にウルサシと云へり。其後弟の右大臣、兄の左大臣を殺して弟右大臣流〻也と有る(私は何かで「右大臣道眞は流罪となり、左大臣時平は都に止まつたので、時の人が
本朝書札往來に相勸めて穴賢と云ふなり土窠(古は穴居す)の穴賢く閉塞してと説明して居る。恙虫 を防ぐべしと言ふなり
萬葉假名として阿安伊以於遠が用ひられ、其が片假名のアイオ、平假名のあいをに變遷したことは今の派生した事項には數へまい。然るに萬葉假名のいはゆる戲訓に至りては奇想天外より來るともいふべきが有るから日本化せられたの最高峯かも知れぬ。
魁帥者大毛人也と註せるは、蝦夷人なれば毛人髮にて事の繁き即ちこちたしを寫せるもの)。